小久保眞「未来の子供たちのために」
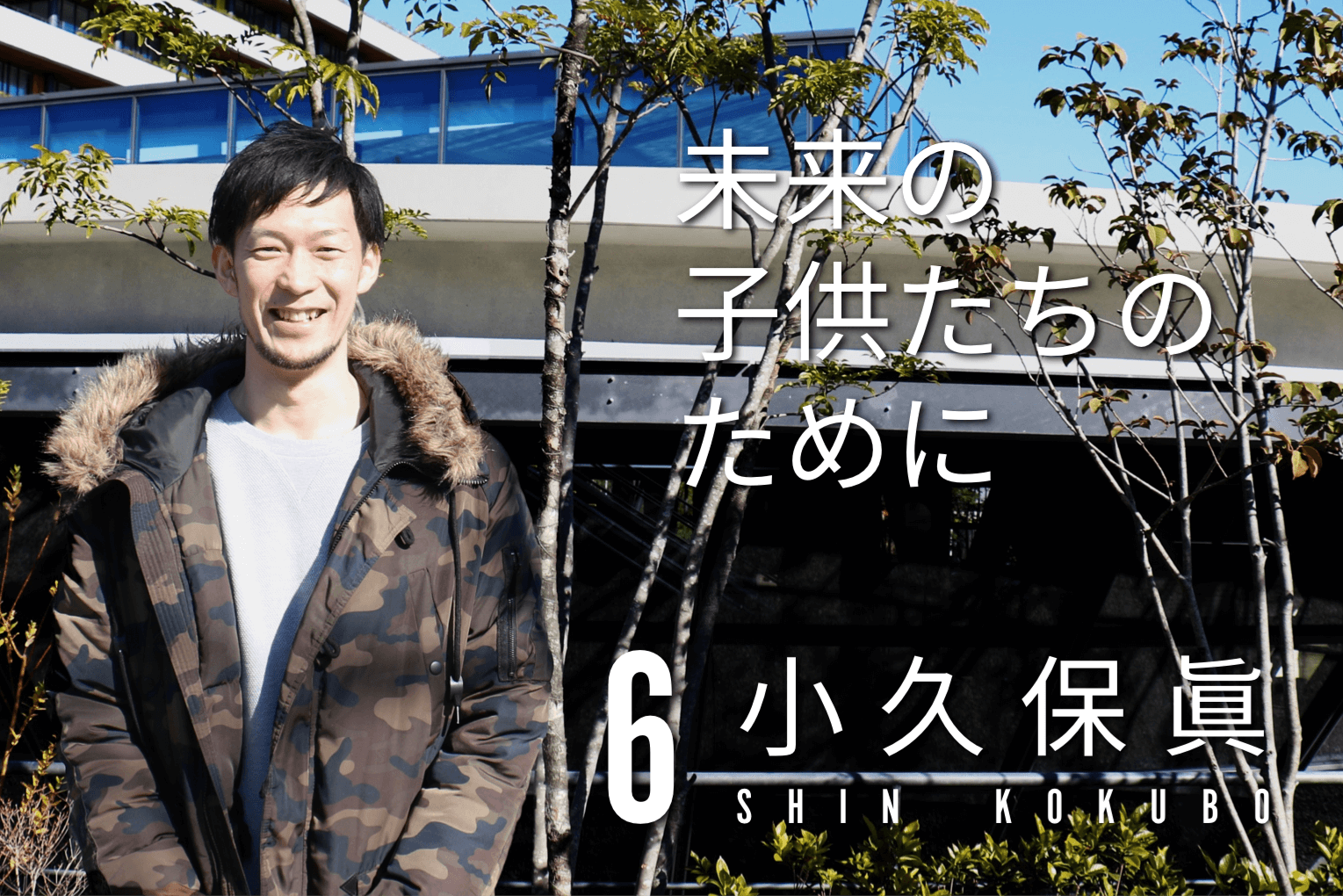
東京Zの盛り上げ番長、小久保眞選手。若手に負けじと声をだし、プレー以外の部分でもチームを引っ張ってくれている。そんな彼のこれまでの道のりを振り返ると、数々の経験をし、紆余曲折を経てプロへの道に辿りついたことを知る事ができた。
初めて夢中になったのはソフトボール
4人姉弟の末っ子として誕生した小久保。決して裕福とは言えなかったが、何不自由なく育ててくれたお母さんには感謝の気持ちしかなかった。
「姉弟で僕だけ少し歳が離れていたので、末っ子ということもあり、すごく可愛がってもらっていました。母子家庭だったのですが、特に何か変わった事とかなく、逆に他の家庭よりも親が一生懸命頑張っている姿をみれていたので、親に対しての感謝の気持ちは幼い頃からありました。もちろん昔は照れくささとかもあって、変に突っ張ってみたりして素直になれない時期もありましたけど(笑)。自分が親になってみて親の凄さを感じましたし、子供のために人生を捧げてくれてたんだなって改めて身に染みました。僕が就職した時には、子育てから解放されて楽しんでほしいなって思いましたね。」
初めてやったスポーツは野球。しかし長くは続かず、次に始めたのが小学校6年生の頃に入部したソフトボール部だった。
「最初の野球は低学年の頃で、とりあえず近所のお兄ちゃんがやっていたから俺も入りたかったというだけでした。まともに練習に入れるわけでもなかったので、楽しくなくてすぐに辞めてしまいました。初めて打ち込んだのがソフトボールでしたね。ちゃんと1年間やりきりました!」
県内ではソフトボールが盛んということもあり、中学校へ進学をすると、野球部やリトルリーグへ入る子供たちが多かったとか。小久保自身も、進学をしたら野球部に入ろうと心に決めていたが、「グラウンドの広さの問題で、野球部がなかったんです。」という結末が。
「どうしようかなと悩んでいた時に声をかけてくれたのが、バスケ部の顧問をしていた先生でした。その先生は小学校のソフトボール部の外部コーチをしてくれていた方だったんですよ。野球部があったら野球をしていましたね。」
背の順で並ぶと後ろから2,3番目になるくらい、比較的身長が高いということもあり目をつけられたとか。言われるがまま始めたことが、小久保のバスケットボール人生のスタートとなったのだ。

目標は“身近な先輩”
バスケットにはまったきっかけは?と質問をすると、「うーん、徐々に好きになっていったのと、先輩に追いつきたいという気持ちですね。」という答えが。“バスケットしかないからバスケットをしていた”ところから始まり、他のスポーツよりもかっこいい気がして続けていた。当時、マイケル・ジョーダンの名前は知っていたが、テレビでNBAを見れる環境でもなくプレーする姿をちゃんと見たこともなかった。そんな小久保にとって、1番身近でかっこよくプレーをする先輩が憧れの目標となっていった。
「初めてバスケットを見る人にとって、ちょっとでも上手い人って凄い人に見えるじゃないですか。“なんでそんなにシュートが入るんだろう”って(笑)。そういう先輩の姿を見て、“かっこいいな。自分もあんな風に上手くなりたい”と思って練習に励んでいました。」決して強いチームではなかったが、部活動を毎日楽しく日々を過ごしていくなかで、3年生の時に長崎市の選抜メンバーに選ばれることに。その実績から、当時県内で1番強豪と言われていた私立瓊浦高等学校から特待生の話を得られることとなったのだ。
「中学校自体に特待生の話がきたのも初めてで、学校側も慎重になって、担任の先生がなかなか僕にその話がきているのを教えてくれなかったんですよ。ちょっとやんちゃな生徒だったからか(笑)、周りは受験でピリピリしている中、早くに進路が決まったことを伝えたら学校に来なくなって悪影響になるんじゃないかって考えていたみたいです。母親と呼び出された時には、“どんな説教をされるんだろ”って思いましたけど(笑)。」という、エピソードもあったとか。
特待生のため学費は免除。学校のこともバスケ部のこともよく知らなかったが、家庭への負担が軽減できるという想いもあり進学を決め、高校3年間は文武両道の日々が続いていった。
エリートには負けない
瓊浦高等学校のバスケ部は、Aチームと呼ばれる主力チームは全員特待生で各学年5名ずつの少数精鋭。一般で入部した選手でのBチームも存在したが、そこからAチームにコールアップされる選手は、数年に1名いるかいないかのレベルだった。
「練習はもちろん厳しかったですが、皆特待生なので、勉強もちゃんとしないといけないですし、生活態度も全生徒のお手本になるように心がけないといけなかったです。中学校はぬくぬくと楽しく暮らしていたので、“とんでもない所に来てしまったな”と思いましたね。そのお陰で、当たり前のことが今までできていなかったんだなって気づけましたし、大人になった今も実になっています。バスケだけでなく、人としての基本が身につきました。」
本格的にバスケットボールを始めたのも高校から。小久保の代は“不作の年”と呼ばれ、苦悩の時間を多く過ごした。
「それまでの先輩の代は、“中体連優勝メンバー”とか華々しい選手が揃っていたのですが、僕らの代にはそういう成績を残した選手が1人もいなかったんですよね。周りも“瓊浦高校、急にどうしちゃったの”って言うほどでした。ただ、そのギャップが僕たちの雑草魂に火をつけたと言いますか。3年生の時の合言葉は、“エリートには負けない”でした。その言葉を胸に、それまでの先輩方の指導もあって、慢心せず、どのチームよりも自分達に厳しく練習ができていたと思います。」
出場記録が続いていたインターハイも、小久保達の代で止まるのではと囁かれていたとか。高校時代も身近な先輩が1番の憧れであり、目標。“これまでの先輩たちが築いていた歴史を汚すわけにはいかない”そんな想いが、学年を重ねる毎に強くなっていったという。
「3年生の時、他のチームが優勝候補と言われていた中、優勝をしてインターハイ出場を決めた時は全員で泣いて喜びました。確か、1点差とか劇的な勝利だったんですよ。本当に嬉しかったです。
決勝の印象が強すぎて、その後のインターハイのことはほとんど覚えていないくらい。ただ、最後に負けた相手が、かず(東京Z#10中川和之)のいた豊浦高校でした(笑)。」

東京に行けばチャンスがある
高校卒業後、大学への進学の話もあったが、インターハイへ出場できたということで、“やりきった”という気持ちがとても強く、バスケットを続けるという想いが残らなかった。
「3年間思いっきりやったので、進学しバスケットボールを続けるという選択ではなく、僕達の代は全員引退し就職をしました。あと、僕等の学生の頃って、特に地方だと、地元で普通に就職をする人が多かったんですよ。プロの選手を目指すっていう考えはほとんど持っていなかったですね。今はBリーグができましたが、もし当時そういうリーグがあったら、僕に限らず選択肢が増えた選手はいたと思います。裏を返せば、今の子供達にはBリーグがあるので、1年目プレーしている僕らが、そこに対して夢の持てるような、キラキラ輝いて見えるバスケットボールリーグにできれば、きっと、今の子供達の選択肢はもっと増えていくと思います。自分達の子供の頃って、“プロって何?”と、思っていましたから。」
お母さんへもこれ以上負担をかけたくないという想いもあり、仕送りの一つでもしようと就職することを決意。長崎に残って狭い枠組みの中で世間を知らずに終わるのが嫌だという思いから、東京での就職先を探し始めた。
「日本の中心である東京へ行けば、何かチャンスがあるんじゃないかと思って東京での求人を探しました(笑)。」そこで見つけたのが、長崎に本店を置く某老舗カステラ屋さんの東京支店。寮もあり、生活の負担も軽減できながら、念願の東京生活がスターをした。しかし!3ヶ月程経った頃、ある事に気づいたのだ。
「そこのお店は東京支店であっても長崎出身の人しか採用しないんですよ。皆、同じ寮にも住んでいるので、日本の中華街じゃないですが、そこが長崎県人会の集まりみたいな場所になっていて、“せっかく東京に来たのに、これでは意味がないだろ”って気づいたんです(笑)。もちろん、周りの先輩とか皆さん大好きだったんですけど、自分の人生に影響がある出会いとか、当初の目的と違うことしてるなって思って。それと同時に、凄いバスケがしたくなったんですよね。」
体を動かしたくてうずうずし始めた小久保は、バスケができる場所を調べ、練習に参加をできるところに顔をだすようになった。色々な所に参加をするにつれ知り合いも増えていき、当然どの人よりも上手くプレーするため「君上手いね。今度うちのクラブにも遊びに来なよ。」と、徐々に強いチームへステップアップしていくようになった。その中で、当時世田谷区で有名だったチームで出会ったのが、現在のアシスタントコーチである斎藤卓だった。
「そこにいた選手は、元々実業団でやっていた方もいるくらい皆上手かったですね。自分は運動能力だけでやっていたので、それだけではないバスケットに触れる時間が増えて、バスケの深みにはまっていきました。」
当時の印象を斎藤ACにも聞いてみると、「第一印象は、爽やかな好青年。高卒だけどしっかり仕事もしていたし、挨拶もできてたしね。バスケの方は、身体能力はあったけど、プレーはかなり粗削りでIQは高くなかった印象かな。でも、色々なことを吸収しようと貪欲で、新しいことにもどんどんチャレンジするタイプでした。」
そこからまた他のチームにも顔をだすようになり、神奈川でストリートを中心に面白い事をやっているチームがあるよと紹介をしてもらったのが、現在SOMECITY TOKYOで活躍をしているTEAM-Sだった。
「僕が最初TEAM-Sに行って、“面白いとこがあったから行きましょうよ”って卓さんにも声をかけました。当時音楽を流しながらバスケをやるっていう習慣がなかったのに、体育館に行ったらDJブースが置いてあって、DJが音楽を流す中でバスケをやっていて、“なんだこのチームは”ってびっくりしたのがTEAM-Sの印象です。4,5年活動してたかな。3on3の大会のエキシビションマッチで試合をしたり、様々なバスケットボールのイベントを主催、運営したりと、他のクラブチームには無い魅力があって楽しかったですね。チームにいる皆の人柄にも惚れて、どっぷりはまりました。高校の延長で楽しくバスケットをやっていたところから、人前でバスケットをして、観ている人に楽しんでもらうということを教えてもらいました。」
プロでやっている選手との交流も増え、レベルの高い所で再びバスケットを始めた小久保の中に、また熱いものが生まれ始めてくるのである。

光を浴びる場所でプレーをしたい
「かずもその1人なのですが、大学で華々しく同年代の選手が活躍している話を聞く機会もあって、もし辞めずに大学でバスケを続けていたら、もしかしたら自分もそうなれたんじゃないかって変な悔しさがでてきたんですよね。かずとかに比べたら全然上手くなかったですし、有名な選手ではなかったですけど、同期で対戦したことがある選手が光を浴びているのをみたら羨ましくなってしまって。頑張れば自分も光を浴びる所でプレーできるんじゃないかって思い始めたのが、プロを目指そうと思ったきっかけですね。」
TEAM-Sの活動と並行して、GYMRATS(現在も選手として活躍する岡田卓也氏が代表を務めるチーム)で青木康平や岩佐潤と共に北米独立リーグのABAサマーリーグにも挑戦。アメリカでバスケットをするだけで刺激になったが、練習環境が揃ったなか、1週間丸1日体を動かす時間を過ごし、“プロ選手は、きっとこういう生活をしているのだろう”と、肌で感じる毎日だった。
色んなきっかけが重なり『自分もプロのステージでバスケがしたい』という想いが強くなった小久保は、岡田氏の後押しもあり、鹿児島県に新しく立ち上がったレノヴァ鹿児島(現鹿児島レブナイズ)のトライアウトを受けることを決意。生え抜き選手として、8シーズンプレーをすることとなった。
プロ選手としての道を切り拓いたが、現実は厳しく、1年目はほぼプレータイムがもらえなかった。
「自分自身の人生、上手くいかないことが多くて、それでも諦めきれずにしがみついているというか。諦めたら失敗だけど、チャレンジし続ければそれはまだ失敗ではないわけなので、1年目プレータイムがほぼなかったですが、諦めずにやり続ければいつか成功するだろうと思って練習に励んでいました。」
前だけを見据え積み上げていったものは確実に芽を出し始め、毎年プレータイムは伸びていき、2年程膝の機能障害でプレーができない苦しい時期も過ごしたが、最後の2シーズンくらいからはスターターとして出場するまで成長を遂げた。そして、2013-14NBDLオールスターではF/C部門で選出され出場。ファンにも愛される選手となっていった。
「プロ選手って、触れられないというか、キラキラしている存在じゃないですか。僕の場合は、脱サラをしてプロになったっていうところに、他の選手と比べると親近感を持ってもらえたところがあるのかなと自分では考えています。オールスターも、上手くいかないけど諦めずに頑張っている姿を応援していただいたことが、決して上手くない僕がファン投票で選んでいただけたとこに繋がっているのだと思います。鹿児島では色んなことがありましたが、ファンの皆さんをはじめ、支えてくれる方がいたからこそ、8年間バスケットができました。」
引退するまで鹿児島でプレーをしようと心に決めた時期もあったが、Bリーグが発足し、自分の可能性を広げるためにも移籍を決意。対戦相手として戦うなかで、選手1人1人がコーチの考えをコートで表現しようとしているのを肌で感じたアースフレンズ東京Zに興味を持ち、自らチームへ声をかけ、練習に参加をし、選手契約へと結びつけたのだった。
チーム内では、中川和之・中村友也と共に最年長選手。ベテラン選手として、現在の心境を聞いてみた。「選手としては、プレータイムが伸びず、試合にも出れない日も多くて満足なんかはしていないです。ただそれは環境が悪いとかではなく、自分が悪いだけなので、そこを打開するためにちゃんと考えながらやっていかないといけないなと思っています。東京にきても、Zのファンの皆さんが迎えてくれて、試合の後ハイタッチで回っている時に“もっとプレーしているところが見たいよ”とか“悔しいけど頑張ってね”とか声もかけていただいて、そういう温かいファンのいるチームにこの歳でも来れたことが嬉しいです。支えてくれている人達に、良いプレーを見せて、チームも勝って、一緒に“やったね!”と1つでも多く喜びあいたいですね。」
コートに立てるのは5人だが、試合にでて戦うのはチーム。ベンチにいるメンバー、そして会場にいるファンの皆さんも含めて1つのチームだと思っていると話す小久保。ファンの人達も、声を出し、手を叩いて一緒に戦ってくれているという言葉が印象的だった。
「試合に出れないからとか、良いプレーができなかったからという理由で、ベンチにただいるって状態なのはあり得ない話なので、誰よりも声を出してチームを鼓舞したいと思っています。もちろん僕も人間なので、ずっと出し続けるって言うのが難しい時もあるかもしれないですが、いつでもそれができるように、胸の中で自分を押し上げていきたいです。やっぱりその試合に出れないのは辛いですが、一緒に戦っている仲間として、声を出すことでチームが少しでも良くなるならそれは1つの仕事だと思うし、それをすることによって、実際に自分がコートに立った時にコートの中の選手と温度差なく一緒に戦えると考えています。逆にぶすっとした態度で座ってて、いざ呼ばれた時に良いプレーなんか絶対にできないので、同じテンションで戦うために常に準備はしています。」
与えられた時間のなかでしっかりアピールができるよう、常に準備が大事になっていると話す姿に、厳しい時間が続くなかでも、諦めず自分と向き合い、チャンスを逃さないよう前だけをみる力強さを感じた。
インタビュー中、「未来の子供達にバスケットに夢を持ってもらえるよう、今自分ができることを精一杯やりたい。」そう話もしてくれた。Bリーグ元年にプロ選手として活動できることに感謝の気持ちを持ち、小さな一歩かもしれないが、子供達に夢を届けられるよう小久保の諦めない姿勢は続いていく。











